虫送り資料室-2
Reference room - 2
高橋の虫送りの近代史
会津美里町の虫送りについての記述は筆者の知る限り文献に乏しく、2001年、旧会津高田町・旧会津本郷町・旧新鶴村が合併し会津美里町になる4年前に発刊された会津高田町史第六巻、民俗各論編IIの中に町の虫送り行事について11行の記述があるのですが、高橋の虫おくりについてはその最後の2行に「会津高田町は古くから虫送りが行われていた地区が多いが、特に特に尾岐窪と冑の虫送りの行事は古くからの形式を現在まで受け継がれていることで注目される」とあるのみ。ちょっと寂しい限りです。
ですがそれ程までに、日常に根付いていた行事であり、わざわざ文献として記録に残すほどでもなかった、という事なのかもしれません。
いずれにせよ、かつては町内の何処の集落でも行われていたこの行事が、今や数えるほどでしかなくなってしまった現状と時代、そして社会の変化にはやはり一抹の寂しさを感じます。
さて高橋の虫おくりの話に戻ります。
前出の通り、記録されている文献はごくわずかなのですが、調べを進める中でとても素晴らしい文献と出会うことができました。
平成二十一年。西暦2009年に町のアマチュア郷土史家、故田中常意さんが町内の年中行事を記録した「年中行事の今昔」という手書による手作りの冊子です。
生前、田中さんが各地区の故老たちから聞き取りを行い、文章化したとても貴重な一冊で、その中に、高橋の虫おくりについて前出の町史よりも詳しく記述された箇所がありますのでご紹介したいと思います。
尚、故田中常意さんの大変貴重なお働きに改めまして心より敬意を表します。
「年中行事の今昔」より
七月十九日(うるう年は十八日)土用の虫送り
この行事は、その年の豊作を願い、土用入りの前夜に子供達が田畑の害虫を取り集め紙などに包み、「虫送り」と書いた旗を立てて「稲の虫送んぞー」と大声で叫びながら、集落の中を廻り歩き最後に村はずれの川に流すというのが、高田近辺の古くから伝わってきた、子供を主役とする虫送りの状況であった。
昭和十年頃からは、この行事も次第に姿を消し始め、今では見られなくなり誠に惜しい事であるが、当町に只一ケ所、いや二ケ所と言おうか、古風な形をそのまま残して行われている地区がある。それが高橋の虫送りである。
この虫送りのことについては、高田町誌(昭和41、12、25発行)と町教育委員会が平成五年二月に発行した「会津高田町の文化財」という本に載っているが、篭作りや行列のことでもう少し知りたいと思い、平成十一年の春に元冑の菊地三郎さん宅を訪ね「西の、冑・小山・仁王地区」の分について伺った。
先ず虫送りの行事は虫篭作りから始まる。虫篭はY型になった二股の胡桃の木四本を骨組み(四つ角)にし、外に雑木や茸・青茅・藤蔓・朴の木等の材料により八十センチ位の篭を作り、屋根は家のように切り妻にし、上部には青茅などを部厚く入れ、屋根の表面と篭の周囲を朴の葉で覆う伝統がある。篭の上部には「萬蟲送り」と書いた旗を立て、紫陽花や立ち葵などの花を挿し、飾るというが、この飾りだけが子ども達の出番のようだ。
この虫篭作りだが記録もないので定かではないが大分古く、昔から上冑に居を構えている四軒(現在も四軒しか居住していない)の家の主人と中冑に住む一軒の家の主人(中冑には五、六世帯が住んでいる)の五人で代々篭作りを継承してきた。最近になって中冑の主人が亡くなり女世帯となったため四人で作っているという。作業をする際は、その人達の座る場所も決まっているそうだ。
虫篭作りは昔は二日位要したそうだが最近は当日一日で仕上げるという。作る場所は村の神社内であるが、作業中場所の閉鎖や入室禁止にはしないが、関係者以外は遠慮を願っているとのことである。
こうして出来た虫篭は、昔から区長元で人夫二人を雇い上げこれを担いでもらい、区長は羽織袴で(現在では背広姿の人もあるという)弓張り提灯を持って先頭になり出発するのであるが、行列的なものではなく、大人も子供も「付いて行ってみるか」という人達が後に続く程度だという。
午后六時上冑を出発、中冑、元冑(現公会堂前)を経て小山の入口に至り、此処で小山の区長と人夫に引継ぐ。その際特別の決まりなどはなく「引継ぎます。よろしくお願いします。」引受けた方では「ご苦労さまでした。」の挨拶程度のもので、引継ぎが終了すれば冑の人達は帰るという。小山の区長達も冑の人達と同様虫篭を仁王の小学校の処まで担ぎ、仁王の区長に同じ要領で引継ぎ、最后に仁王の区長達が高橋の橋の上まで送るのが通常の経路になっていたそうだ。
昔からの伝統で担いでさがった虫篭も昭和の初め頃からはリヤカーに乗せてさがるようになり、更に車社会になって暫くしてから、上冑の人が同じ経路をたどり、引継なしで仁王の船岡山の入口まで自動車で直送するようになったという。そこからは仁王の区長が時間を見て、人夫の二人が担いだ虫篭の先になって高橋の橋の上まで送るように変わってしまったということである。
一方、東の尾岐窪の分については平成十一年十月高田厚生病院内に入院していた尾岐窪の佐瀬政喜(八十八才)さんから虫送りの話を聞くことができた。
尾岐窪の方の篭作りは、昔は部落内の高学年から小学生までの男子が活躍した。数班に分かれ作業の内容がきめられ詰所(陣屋とも言う)と、篭を作る場所作りから始まる。七、八十年程前は高等科(昔の尋常小学校時代の高学年)の人が大将(親方)になり、経験者の助言を受けながら、下級生を指揮し作業に当たるのが習わしであった。
詰所や虫篭を作る場所は、住んで居る部落に近い山麓の杉林で内部に二メートル五十センチ四方位の空間があり、傾斜のゆるい、水はけの良い所を選び周囲の立木を利用し、地上より高さ七十センチ位の処と、一メートル五十センチぐらいのところに横木を二段に縛り付け、出入口にする所を残してそこに青葉の付いた雑木の枝や萱などで内部が見えないように外側から棚を作って囲う。
詰所と作業をする所は別で大将格の者だけは作業場内に居場所を置いた。
作業の分担は、高学年者は材料集めや虫篭作りの手伝え、小学生の男児は小間使いや藤蔓採りなどをした。藤蔓は細いものはそのまま使うが太いものは叩いて皮をむき適当に裂いて、縄、紐の代りに用いた。この藤蔓だが虫篭作りや詰所造りにかなりの量が必要であり、子供達は杉林内などを捜して採って来るのであるが、此の事は良質の杉を育てるのに大いに役立っているため、山の持主から大変喜ばれているという話もしてくれた。
虫篭作りの骨組みには、二股になった木を二本逆様にして、木元の処で二本一緒に縛り、四つ足の様になった処には、篭を作れる程の空間をとり足を篭の柱として篭を作り、一面は竹で編んだ網を取り付け篭の外部は青萱等で美しく囲え仕上げられるという。
虫篭作りの骨組みには股木を使うが、この形をした木が少ないので手に入れば四、五年ぐらい使い続ける場合もあるという裏話もあった。
作業中は青年の人達が時々来て指導するが分らないところがあると年寄りの人を頼んだり、現地で指導を受けたり手伝ってもらうことにしている。
虫送りの当日は青年の人達が来て最后の仕上げ作業にかかる。先ず青萱で屋根を葺く。次に同じ青萱を長さ七十センチぐらいに切り直径約三十センチぐらいになるよう三ケ所を藤蔓で縛り杭状のものを作り屋根の上に取り付け、その上部中央に幣束を立て、虫送りの旗と紫陽花の花などを沢山差して飾り出来上りである。
こちら東の方では、虫篭作りと並行して面と槍を作る。面は朴の皮で作り槍は細い木を用い穂先を三本にするという。
昔からこのような形で作られてきた虫篭も昭和の末頃からは作業場を村の地蔵堂内に移し、区長が経験者を依頼し二、三人で作るようになったが、更に事情が変り平成十三年頃から、部落内の星清伍さんという方が区長から頼まれ、自宅の納屋に於て一人で作るようになり現在に至っている。作業中は昔同様、作業場の閉鎖がなされるという。
こちらの方の行列だが当日夕方から大人の応援を受け高学年の者が主宰となり、小学校六年生(十三才)の男児が面を被り槍を持って、弓張提灯を持った先頭の区長に続き、年長者が虫篭を担ぎ行列を組み、大人の人が法螺貝を吹きながら高橋の橋の上まで下っていた。
現在もこの伝統を守ってはいるが、虫篭を担ぐ人が中学生から大人に(交代で担ぐので四、五人)変ったことと、最近の少子化により女児も行列に参加させるようになったという話である。
両者橋の上に到着するとそこで東西寺院の住職が虫供養を行ない法螺貝を吹き、虫篭を橋の上から宮川に流される。そのあと、子供達の手作りの灯籠が数十個川岸から流され行事のすべてが終了する。
かなり古い伝統を持つこの虫送り、昭和四十一年七月二十日に町の重要無形民俗文化財に指定された。これに伴い地元では高橋の虫送り保存会が結成され、今後も伝統が引き継がれることになり嬉しい限りである。
この行事の影の力となっておられる方々に感謝と敬意を表し、これからも子ども達の豊かな心と夢を育て、美里町の宝である伝統を守って頂きたいと念願する。
聞き書き / 田中常意


昭和57年の
高橋の虫送り
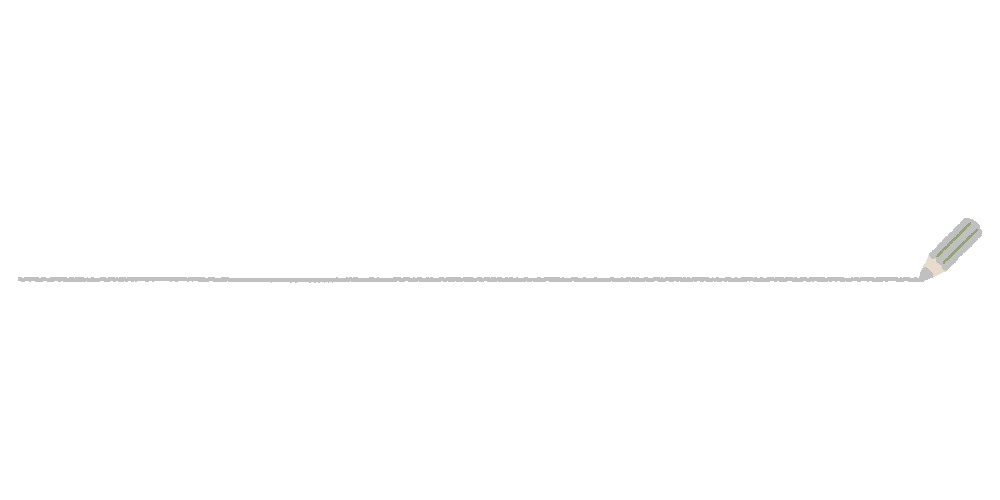

冊子の表紙。尚、会津美里町図書館に所蔵されています。
