虫送り資料室-4 (西日本)
Reference room - 4 (Western Japan)

【いもち送り】滋賀県近江八幡市北部
当地域では害虫を「いもち」とも呼ぶ。当地域では1965年(昭和40年)頃に途絶えたが、1980年(昭和55年)、地元・大嶋奥津嶋神社の深井武臣宮司の声掛けを機に、地域の伝統行事を継承しようとの機運の高まりと共に復活した。地域の水田を歩いて巡る際は「いもち送れー、いもち送れー」と唱えて廻る。



【虫送り】滋賀県竜王町
竜王町では、稲の害虫を追い払い五穀豊穣をお祈りする「虫送り」を行ってきました。
かつては各集落で見られた農村行事でしたが今は限られた集落が伝統を伝えています。
山之上(東出・西出・新村・西山)、田中、橋本、山中、岡屋、小口、薬師、七里、西川、西横関の集落で、6月下旬から7月下旬にかけて行われます。
夕方頃、タネギ(枯れた菜種殻)などでつくった松明をもった村人が集まります。
松明に氏神のご神灯の火で点火すると、賑やかに鉦や太鼓を打ち鳴らしながら、火の付いた松明を持って夕暮れの田の道を進みます。
緑一面の田んぼの中を、松明の火をチロチロ見せ、煙を煙幕のようにはりながら、夕映えの中を鉦や太鼓の音とともに囃しながら進む様子は、素朴でなつかしい農村風景です。
川の上(かみ)の集落から川下(しも)の集落へ虫送りの火を送る習慣が残っているのが、7月16日に行われる(山中は15日)山中―岡屋―小口―薬師―七里の集落です。最初の集落の虫送りの火が村境に来るのを見届けてから、順番に集落から集落へ松明の火を灯しリレーしながら進みます。最後の七里の松明の火が消える頃には、夏の夜空が広がります。
西川―西横関の集落は毎年土用入りから数えて3日目(土用三郎の日)7月22日あたり(閏年は一日ずれる)に西川の吉水神社からスタートし大洞川沿いの田んぼ道を西川の外れまで火を持って行き燃やします。燃やし終わり西横関のかかりに行くと三役さんがご挨拶に来て虫送りが終わります。(昔はそこから西川と西横関と一緒に日野川まで火を運び川に流していました。)
一時期途絶えた虫送りを復活させたのが、橋本の集落です。「子どもたちに伝統を残していきたい」という思いから、子ども中心の祭りとして行っています。まず虫送りの前に大人が子ども達に教えて松明を作ります。当日はお宮さんでお神楽を奉納された後に、子ども達が自分の手で作った松明を持って田の畦道を進みます。地元の方々の願いがこめられた、五穀豊穣を願う「虫送り」行事です。



【多羅尾の虫送り】-滋賀県甲賀市信楽町多羅尾-
信楽に多羅尾という地区がある。藩政期には近江・伊勢・播磨国など諸国の天領を治める多羅尾代官が陣屋(代官所)を構えたところだ。
地区は信楽の山中にあって四通八達の道が交じり合い、伊勢や京道の道標が往時のよすがを偲ばせている。地区の中央を流れる大戸川。その流域に田畑が開けている。要害をなす山塊は風化した花崗岩で覆われ、透き通った川底は赤茶けた花崗岩の砂利。昭和28年、多羅尾は山津波にのまれ多くの犠牲者を出した苦い経験がある。しかし今、多羅尾は見事に復興を遂げた。清流が流れ、山腹にササユリが咲き、ヤマアジサイが美しい。
ササユリ(多羅尾)
多羅尾は高燥、寒冷。気温は信楽の中心街よりさらに2、3度低いとも言われ、ササユリの開花は京都・山城より2週間、丹後や奥丹波、信楽より1週間程度遅い。虫送りのころ、咲きそろう。
6月28日、多羅尾地区の里宮神社の虫送りが午後7時半ころから始まった。神事の後、同8時ころ灯明の火が松明に点火され、氏地の大人や子供が松明を手にして境内を出発。鉦、太鼓を打ち鳴らし、松明がその後に続く。田んぼ周りの道を周回し、村はずれで松明を焼却。
松明の点火から約1時間、虫送りは無事終了した。虫送りが終わると、この地方ではホタル狩りを行わない。ホタルはのびのびと川辺を飛べるというわけだ。しかし、近年、多羅尾においてもホタルの姿をみることもめっきり減ったと土地の人。
例年、7月中旬には祇園祭(里宮神社)が行われる。
虫送りという行事
信楽では虫送り(地方によっては実盛送りとも)を田虫送りという。田虫は稲につくウンカやズイムシ、イナゴなどの害虫の総称。旱魃や虫害は稲の大敵。蔓延すると凶作の原因となる。
虫送りは宵のころ松明を灯し、鉦、太鼓を打ち鳴らし、地区の田んぼのあぜ道を松明を抱えて歩き回り、「田虫送るぞ! 田虫送るぞ!」などと叫びながら村はずれまで害虫を追い払い、駆除する農村の呪術行事。当地区では呪文を唱えることはない。
虫送りはかつて西日本の農村で広く行われた行事。大体、6月下旬ころから始まり土用入りのころまでに行われた。害虫の発生をみてからこれを行うところが多かった。戦後、農薬の普及により害虫の大発生が抑えられ、昭和30年代ころから町村合併などを機会に虫送りの行事も廃絶になるところが多くなり、近年では住民の記憶から消えてしまった。虫送りは時代の変遷とともに失われた祭のひとつといえるだろう。虫送りは「実盛送り」の別称もあり、この行事の淵源を示している。実盛は平氏の斉藤別当実盛のこと。平家物語の「実盛最期の事」の段で綴られた実盛である。伝説によると、実盛は源氏方の手塚太郎光盛と一騎打ちに臨んだ際、稲田の切株につまづき打たれ、その御霊が田(稲)虫になったとされる。虫送りの背景に怨霊信仰があるといえよう。科学的知識が未発達の時代には、予期しない災害が発生した場合、不慮の死を遂げた人の怨霊による祟りという信仰があった。多羅尾の虫送りでは実盛の人形を立てるなど具体の怨霊は示されないが、それを供養することによって田虫を追出す祭といえよう。
信楽では例年、多羅尾の里宮神社(6月28日)や小川の天満宮(7月14日)などで虫送りの行事が行われている。農薬の開発普及によって虫害は激減したが、地区一統の行事として虫送りを行い、子供等が稲作の難しさを知り、ともに共助の気持ちを大切にするという地区住民の強い願いも込められているのだろう。よい祭りだった。-平成24年6月-



7月、虫送りが行われます。上流の上の町と宮の町から太鼓や鉦を叩きながら、たいまつを持ち、「どろ虫出て行け、さし虫出て行け」と唱えながら進み、途中で中の町や下の町と交代し、下流まで害虫を追い払います。どろ虫とは、田んぼの虫で、さし虫とは、人をさす虫だそうです。(京都市文化観光保護財団HPより)


【稲の虫送り】京都府南丹市
山田町では、毎年6月16日に上山田・中山田・下山田のそれぞれの集落でおこなわれています。夕方から夜にかけて各戸から住民が松明(たいまつ)をもって集まり、鉦(かね)や太鼓を鳴らしながら地区の中を練り歩きます。地区はずれの川岸に到着すると松明ごと川へ流して行事は終了となります。
平成12年3月29日付で天理市指定無形民俗文化財に指定されました。(天理市ホームページより)



【針ヶ別所の虫送り】奈良県奈良市針ヶ別所
奈良市の東部山間地区や天理の山間、室生の一部でこの時期「虫送り」という行事が行われています。
「虫送り」とは、田植えが終わり一息ついた頃に発生する害虫の駆除のために行われるといいますが、単に駆除するのではなく、供養を兼ねていることからお寺での供養祭が行われるところも少なくないようです。
ここ奈良市の針ヶ別所では夕闇迫る頃、長力寺で法要が行われました。
法要後、虫送りの松明の火種となる灯明がお堂から広場に降ろされます。
虫送りに使用される松明は各自で作られているようで、その作り方もさまざまでしたが、概ね2メートルくらいで、割った竹または、細い竹を数本束ねて、先の方には良く燃えるように乾燥した杉の葉や、竹の笹の部分が付けられています。
松明に火が移されるといよいよ出発
集落の外側を回り込むような感じで行列が行われます。
先頭は鐘、続いて太鼓、そのあとに松明行列でしたが、途中からは入り乱れています。
最後は一つの場所に集められ終了しました。 (奈良の風景と無形民俗文化財より)



【西原の虫送り】奈良県上北山村西原
こちらは、大台ヶ原と大峰山系の狭間に位置する山村ゆえ、平地は乏しく、現在、西原地区に水田や大規模な畑作は見られない。しかし、なぜか虫送りの行事は延々と受け継がれてきた。240年続いているとも言われる。こちらの虫送りでは、病害虫の退散に加えて、先人達の供養、五穀豊穣などをお祈りする。
以前は七夕に合わせて行われていたようだが、数年前から7月の第1土曜日になったと聞く。西原地区内の白龍山宝泉寺で祈祷が行われた後、和泉地区にある車僧禅師のお墓へお参りをする。車僧禅師は南朝にゆかりのある方で、後亀山天皇の孫で尊慶王と呼ばれたらしい。南朝悲話は吉野各地に残るが、ここ上北山村も例外ではないようだ。
西原では松明のことを松明木(たやぎ)と呼び、こちらの材料はヒノキ材である。細長く割り咲かれたものに枝の部分なども混ぜ、直径10cm程度に束ね締めていく。さらに天井部分からどんどん差し込み、適度な空気孔を保ちながら長さ1m位に仕上げる。私は、あらかじめ用意されたものを持たせてもらったが、今回(2015年)、有料でマイ・たやぎ製作も受け付けておられていた。
さて、午後7時頃、車僧の墓前に御供えした蝋燭の火を使って松明に次々着火する。最終的には、100人近い松明の行列となって、和泉地区を下り下田地区(約2km先)の河原をめざす。道中、鐘の音に合わせて誰からともなく、合い言葉が叫ばれ大合唱となる。沿道には、各家からのお出迎えも多い。
「ちんちん こんこん おーくったー おーくったー」「おーむし こーむし おーくったー」
祭りごとは、やっぱり参加するのが一番楽しい。はじめは照れくさくて小さかった私の掛け声も、大合唱に引きつられてヴォリュームがあがる。この日は小雨模様の一日だったが、不思議と7時頃からは雨足も和らいだ。しかし、湿度が高いのか松明の炎は、例年に比べると小さかったそうだ。翌朝、町並みを歩くと、大行列の跡には、大蛇がすり抜けたかのように、焼け炭の破片が尾を引いていた。祭りの後の余韻も楽しいものだ。



【カンカンプー】和歌山県串本町高富
和歌山県串本町高富で6月29日(2025年)、稲の豊作を願う伝統行事「虫送り」が6年ぶりに復活した。地元住民や子どもたち約50人がたいまつを持ち、「実盛殿のお通り よろずの虫はお供」と唱えながら田んぼの近くを歩いた。
虫送りは、稲の切り株につまずいて落馬し、敵に討たれた平家の武将、斉藤実盛がクロカメムシに化けて稲を荒らすようになったとして、その霊を鎮めようと始まったといわれる。鉦(かね)を「カンカン」と打ち鳴らし、ほら貝を「プー」と吹くことから地元では「カンカンプー」と呼ばれる。 高富地区では30戸以上が稲作をしていたが、現在は5戸に減っている。虫送りは新型コロナウイルスの影響で2019年を最後に途絶えていた。稲作農家でつくる水利組合や区が伝統行事を子どもたちに伝えようと復活させた。
午後6時ごろ、クロカメムシを載せたわら舟を担ぐ人を先頭に、住民や子どもたちが竹のたいまつに火を付けて行列を作った鉦やほら貝を鳴らしながら練り歩き、海岸に到着すると、たいまつを浜に立ててわら舟に火を付けて海に流した。 世話役を務めた濵昌子さん(70)は「子どもの頃から楽しみにしていた。コロナでできなかったことで知らない子どもたちも多くなっているので風習を伝えたかった。こんなに大勢に集まってもらえて良かった。来年も続けたい」と話した。
【宮代の虫送り】兵庫県丹波篠山市
市野々と隣り合う宮代集落にも虫送りの行事があります。
ただ、「これは虫送りだろうか?」と、一見理解しにくい行事ですが、以前の形を聞くと、やはり虫送りだと考えられます。
現在は、篠山川沿いの灯篭の下で燃やしたかがり火からロウソクに火をもらい、提灯で持ち帰ります。
今は皆さん、ほとんど提灯を使われますが、数年前まではカンテラで持ち帰る人もいました。さらに以前は松明に火を移していました。さらに昔は、その松明を持って水田の周りを回っていたということですから、間違いなく虫送りです。水天の周りを回った後、また川に戻っていたのでしょう。
形は変わっても、虫送りの行事が続いていることがすごいことだと思います。



福山市神村町の八幡神社は延久元年(1069)創建と云われ、京都石清水八幡宮の分靈が祀られている。特殊神事としては虫送り、火踊り等がある。社務所の東側に弥生式包含地があり、古くから人々が住みついた場所と伺われる。
この虫送りには、はね踊(はねおどり)が附随する。現在は新暦6月最終土曜日に行われる。



【蝗除祭/虫送り】広島県府中市栗柄町
7月の第1日曜に行われる蝗除祭〈こうじょさい〉(虫送り)は、田んぼなどの害虫を追い出す目的で行われるもの。12の氏子町内が鉦や太鼓を打ち鳴らしながら行列をなして参詣し、境内で盛大に踊りはやす、夏の風物詩だ。


【蟲送り】広島県三次市君田町西入君
田畑の害虫(禍)を祓い、秋の五穀豊穣を願うこの神事ですが、聖神社のある君田町西入君では サネモリさんという人形を作り、それを子ども達が太鼓の音とともに川まで送ります。
これは古く源平合戦の折、斎藤実盛という武将が稲に足をとられて戦死し、それを恨み、稲に祟る蝗になった故事から、里から実盛(サネモリ)さんを追い祓うことで、田畑を守る風習になったとのこと。



【虫送り踊り】広島県山県郡北広島町川戸
田植えがめでたく終わり、稲が成長を始める頃、泥負い虫、ナカザシ、ウンカなど、稲の生育に害を与える虫が発生します。
享保17(1732)年の大飢饉は、ウンカによる被害が原因ともいわれており、先人たちは、このような害虫を追い払う呪法として藁人形を作り、川に流す「虫送り踊り」を行いました。
中部以西では、藁人形を「サネモリさん」と言っていました。サネモリさんは斉藤別当実盛という平家方の武将です。
嘉永2年(1183年)源平合戦において、平家の武将斉藤別当実盛が水田の稲の切り株につまずき、あえなく最期を遂げる際、「我は害虫になって、水田にたたる」と言い残したとの言い伝えがあります。実盛の怨霊が害虫となり田畑を荒らすと考えられ、サネモリ人形をつくり、稲に付く害虫の御霊をこれに移し村境で川に投じて追放しました。
稲の病虫害を防ぎ、五穀豊穣を祈願する農村の大切な祭りが「虫送り祭り」で、サネモリ送りの呪的効果をより高めるために踊られていたのが、「虫送り踊り」であったとみられます。この虫送り踊りは、江の川源流域に古くから行われていた武装行事であり、旧千代田地区では川戸地区に限って踊られていたようです。
虫送り祭りは、民俗行事を伝承するものであり、上川戸熊野神社での神事や腰に付けた小太鼓の音や笛、手打ち鉦の拍子に合わせてサネモリ人形を振りかざしての行列など素朴な踊りが展開されます。



【虫送り】山口県北浦地方
山口の「北浦地方のサバー送り」国の選択無形民俗文化財へ
稲につく害虫を神格化させた「サバーサマ」と、騎馬武者を表した「サネモリサマ」と呼ばれる2体のわら人形を集落の外に送り出すことで、稲の生育と豊作を祈願する。長門市東深川の飯山八幡宮を起点に、各集落が数週間かけて送り継ぎ、最後に下関市の豊北町、豊浦町付近の海に流す。
同八幡宮によると、江戸時代から続く行事で、東深川藤中(ふんじゅう)地区の住民が毎年6月下旬から7月上旬に送り出しをしている。稲作を中心に農業が盛んな地域で行われているが、わら人形の作り手の高齢化や運び手の減少が進み、保存会などがない中で記録作成が急がれている。
「北浦地方のサバー送り」は2009年4月、県の無形民俗文化財(長門市のみ)に指定された。同八幡宮の上田久充宮司(54)は、選択無形民俗文化財への答申を「大変うれしいこと。後継者の育成が今後の課題だ」と話した。
同文化財に選ばれると記録の作成や保存にかかる費用の一部について文化庁から補助が受けられる。長門、下関の両市教委は今後、記録づくりの方法を検討するという。(朝日新聞digital)
**********************************
当地域では、藁を主材として作られた2躯の実盛人形を長門市東深川藤中ふんじゅうから下関市豊北町粟野まで送り継ぐことで稲虫の災禍を追い払う。2躯の実盛人形は共に長さ約2メートル・高さ約1メートルの騎馬武者姿で、それぞれに「サバーサマ」「サネモリサマ」と呼ばれるが、前者はウンカである稲虫の化身であり、後者は斎藤実盛の霊を指すという。実盛人形の基となる藁人形は、東深川藤中にある飯山八幡宮社務所で、8名の氏子によって送り継ぎの始まるおよそ1週間前に作成される。その藁人形は八幡宮宮司に引き継がれ、送り継ぎ開始前々日までに、和紙に書いた顔、和紙で作成された兜、羽織の代わりとされる和紙、木の刀が着けられ、騎馬武者姿に仕立てられる。兜と羽織には毛利家の印である「一○」が記される。この後、送り継ぎ開始当日までの2日間、八幡宮で虫除けの神事が行われる。送り継ぎは先の藤中から中山・江良・上郷の順に二十数か所の集落で行われる。その後は年によって違うが、人形は送り継いだ地域の住民によって抱えられ、西深川境川を経由した後、日置上長崎へきかみ ながさこ(旧・大津郡日置上村長崎)まで運ばれる(※2010年代現在は経路の多くで軽トラックが使われる)。その後は、各自治会や子供会などの手で数週間かけて各地域を送り継ぎ、下関市豊北町粟野(かつての豊浦郡粟野村。江戸時代における長門国豊浦郡粟野2か村、幕藩体制下の長門府中藩知行粟野2か村)まで運ばれる。粟野以降の順路は決まっていないものの、最後は、多くの場合は海(油谷湾)に流され、時には燃やされる。
(wikipediaより)



【なむでん踊り】山口県周防大島町
なむでん踊りとは、毎年田植え終了に行われる「虫送り」の行事です。
鐘や太鼓の激しい音の響きによって悪虫悪霊を追い払おうと考えられたものです。
邑智郡邑南町矢上の鹿子原に残る民間信仰行事の一つです。虫送り行事は昔は全国各地にありましたが、農薬の普及などですっかりすたれ、原型を留めるものは少なくなりました。
毎年7月20日に行われる、「鹿子原の虫送り踊り」は古型を残す全国でも数少ないものといわれ、昭和42年(1967)5月県無形民俗文化財に指定されています。花笠に浴衣、紅だすき姿の若者たちが腰に太鼓をつけ、乗馬姿のワラ人形を中心にくり出し、独特の「虫送り唄」に合わせて行進、やがて村はずれの川に人形を流します。ワラ人形は平家の武将、斎藤別当実盛(さねもり)を型どったもので、実盛は源氏の兵に追われたとき、水田で稲株に足をとられて討たれました。
このため死後、ウンカとなって稲を食い荒らすようになったといいます。そこで実盛を慰め、無事に村から送り出してしまおうというのが同行事の由来で、ウンカをサネモリと呼ぶ地方もあります。(しまね観光ナビより)
.jpg)

.jpg)
火で稲の害虫を追い払って豊作を祈る伝統行事「虫送り」が、阿南市長生町の桑野川堤防沿いで行われた。
かねや太鼓の音が鳴り響く中、地元の住民ら約100人が、たいまつを掲げて行進。田園地帯に約100メートルにわたって炎の列ができ、幻想的な光景をつくり出した。約50人の子どもも、みこしを担いだり、LEDで作ったちょうちんを持ったりした。
虫送りは、平安時代末期の武将斎藤実盛が稲につまずいて討ち死にしたことから、稲を恨んで害虫に化けたという伝説に由来し、実盛を供養して五穀豊穣を祈願する。言い伝えを説明する住民制作の紙芝居も行われた。
茨城県水戸市から里帰り中に子どもみこしに参加した中山寧音ちゃん(4)は「おみこしは楽しかった。紙芝居で虫送りのこともよく分かった」と話していた。 (徳島新聞より)

【虫送り】香川県小豆島町
小豆島では、肥土山と中山で存続している。かつては一帯を潤す伝法川に沿って、最も標高の高い上流域の中山地区(現・小豆島町中山)から始まり、翌日に中流域の肥土山地区(現・土庄町肥土山)、そして最終日には下流域の2集落(黒岩、上庄)へと、日をずらしてリレー方式で順に行い、最終的に海へ虫を送り出していたという。
現在は市街地化した下流域の平野部では行われず、中山の虫送りは肥土山の虫送りの翌日に行われている。肥土山自治会の史料によれば、伝法川流域における虫送りは、江戸時代初頭にあたる寛文元年(1661年)に始まっている。



松野町の延野々(のびのの)地区で毎年開催される虫送りの行事は、五穀豊穣を願い、 作物が虫に食べられないよう、太鼓・鉦に松明(たいまつ)をかざしながら水田の間 を練り歩く、地区の伝統行事です。
例年、あたりが暗くなる頃から、地区の子供達や住民の方々が集まり、松明に火が 灯されて虫送りが始まります。
6月に稲の害虫が死ぬように、死去して仏になる
塚の日(2日、5日、20日)にサイトコベットコサイノモリ 稲の虫は西へ行けという掛け声と共に長さ1mの大ワラジを担ぎ、太鼓やほら貝、鳴り物を鳴らしながら田の畦を練り歩いた後、神社で参拝します。
田植えが終わって農家が骨休めをする「田休み」を兼ね、各家の苗床に柿の葉、米、煮干、シバ餅、お神酒などをお供えし田んぼの神様である「オサバイ様」も祭られます。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
【椿山虫送り/太鼓踊り】高知県仁淀川町
椿山の太鼓踊りは年に4回奉納されます。6月、8月、9月に行われ、8月は氏仏・若仏祭と盆供養があり、8月の盆供養と9月の奉納は夜に行われます。
6月の虫送りの際には氏仏堂だけでなく、地区内を回り、急な坂を下って谷に行き、そこでも太鼓踊りが奉納されます。
約600年以上も続く伝統行事の「虫送り」は、平安時代、斉藤別当実盛(さいとうべっとうさねもり)が源義仲(みなもとのよしなか)に敗れ、亡霊が稲の害虫になった言い伝えから、供養と豊作を祈ったことが起こりといわれています。椿山虫送りの時に奉納される椿山の太鼓踊りは、安徳(あんとく)幼帝の子守歌、平家のゆかりの霊を慰める踊りとして椿山集落に受け継がれ、町の無形民俗文化財に指定されています。
池川中心部から車で約30分の奥山にあるこの椿山地区。標高約600メートルにあり、山肌の急傾斜に集落の家々が段々の棚田のように建っています。まさに「天空の山里」という光景。平地が少ないので田畑も段々。家から見える風景は、間の深い谷の向こう側に、山々の緑が目前に広がり、場所によっては滝の姿も見えます。昭和50年代中頃まで焼畑が行われ、ミツマタやそば、麦などを栽培していました。50年前には約150人が住んでいましたが今は6世帯9人の集落です。
【虫追い祭り】福岡県久留米市田主丸町
田主丸地域で3年ごとに行われる伝統行事。
「虫追い」とは、本来、稲の害虫を鉦や太鼓を打ち鳴らし、夜は松明をつけ追い払うのが目的でした。しかし江戸時代、虫追いをした地方は、害虫のせいで米の出来が悪かろうと、年貢が割り引かれたとのことで、年貢をまけて貰うための行事でもありました。以前は全国各地で行なわれていましたが、現在はいくつかの地域でしか実施されておりません。田主丸地域でも古く江戸時代から行なわれていましたが、戦後しばらく途絶えていました。
「虫追い祭り」は、竹とわらでつくった馬を30数名の若者が肩で担ぎ、人形は、鉦・太鼓のお囃子に合わせ、会場を練り歩き、合戦を行う勇壮な一種の喧嘩祭りです。町内各地・商店街などで合戦を行う昼の部と、松明を灯して巨瀬川の中で合戦を行う夜の部で、祭りは終了となります。
この祭りを昭和52年に復活させ、以来3年ごとに開催されています。
【国宝臼杵石仏火まつり】大分県臼杵市
国宝臼杵石仏火まつりは、地元に伝わる「虫送り」 「豊作祈願」 「地蔵祭り」を発展させたものです。
千本の松明で深田の里を彩り、石仏群の前に篝火を灯し、「火に映える石仏」「石仏の里の神秘さ」を創出します。
.jpg)

.jpg)
【宮熊の虫送り】大分県宮熊地区八幡神社
虫送り行事とは、稲の病害虫をはじめとする病気や各種災害などを追い払う風習であり、大分県では湯布院のこうじょう祭りなどが見られる。
宮熊地区の虫送り行事の特徴として、全国的に薬人形(実盛人形)を用いる例が多いことに対し、麦薬で作った神興を用いられ、全て地区のこどもたちにより祭礼がおこなわれ、神興自体が濃厚に密接に関与している点があげられる。
その他詳細は別紙パンフ及び概要書に記載のとおりである。
【有水鉦踊り】宮崎県都城市
有水鉦踊りは有水備前守の命日である8月4日に行われる農耕儀礼です。まんじゅう笠を被った鉦3人と矢旗を背負った太鼓9人で構成され、鉦を中心に外側を太鼓で囲み歌い踊ります。踊りの服装や形は、臼太鼓踊りや各地の大太鼓踊りに似ていますが、3種の鉦が主となっている点が特徴です。また、歌詞の中に実盛の名が出ており、全国各地に広がる斉藤実盛の「虫送り」行事の変形とも考えられています。
【由来】
寛永年間(1624~1644)に、有水地域で稲の虫害や、牛馬の疫病が広がりました。生活が困窮した住民はこれらの被害を有水備前守※の祟りと考え、社祠を建立し、鉦踊りを奉納しました。その結果、その年は災害を逃れて大豊作となり、安穏な生活に恵まれたため、鉦踊りが続けられることになったといわれています。
※有水備前守とは、有水地方を領した伊東方の武将であったと思われ、島津方との戦いで敗戦が続き、天正18(1590)年8月4日に自領の前で馬の足をとられて無念の最期を遂げました。 (宮崎県都城市HPより)


【除蝗祈願祭】宮崎県宮崎市宮崎神宮
虫宮崎市の宮崎神宮では、農作物を病虫害から守り、五穀豊穣を祈る「除蝗祈願祭」が行われました。 「蝗」を「除く」と書く「除蝗祈願祭(じょこうきがんさい)」は、宮崎神宮で毎年7月10日に行われている伝統行事で、害虫などによる被害が出ないよう五穀豊穣を祈るものです。 10日は祝詞が奏上された後、巫女が「豊栄の舞」を奉納しました。 このあと、参列者は神前に玉串を捧げ、今年の豊作を祈願していました。
【ウプリ(虫送り)】沖縄県多良間村
【多良間島】
1.ウプリ(虫送り)
昨年10月始めて多良間島に出かけた。このときの民俗と心象風景は『多良間島』として記しておいた。この島の年中行事については、ふるさと民俗学習館の垣花昇一さんから詳しい説明を受けていた。
行事では旧暦2月下旬におこなわれるウプリ(虫送り)が気懸かりになった。虫送りは沖縄本島でもかつては稲作農耕に伴う行事として、シマクサラーの名称でひろく行われていた。地誌などによると、鼠やバッタなどの害虫を浜から舟に乗せて流すのが一般的といえる。
ところが多良間島のウプリは、①虫を捕獲するところが決まっている。②浜の近くにある洞窟で虫送りの祈願をする。③流すのではなく海に入って決まった地点で沈めるというのである。
4月12日に実地見学を許されたので概要を記しておきたい。
多良間島は一島一村の行政単位で多良間村を形成している。集落は南北の中央道を境に西側を仲筋、東側を塩川とし、ウプリもこの2字で行われてきたが、塩川では中止しているという。
虫取り地点・・両字ともポーグ(抱護林―集落を囲んだ林)から南へ1~2キロメートルの地点である。仲筋はカミディ(亀出)といい、ポーグをしばらく走ると道路が二股に分かれたところにある。説明看板も何もなく、ただ岩が道路の中に取り残され、雑木や草が生い茂るだけである。草刈も何もしないという。
塩川の虫取り地点は、タニカー(高穴)の畑の一角にあるユウヌフツと呼ばれる場所である。ここも仲筋と大差なく岩が開墾から取り残されたようにあり、草木も自然のままで繁茂している。いかにも虫たちの住処にふさわしい。
今回は虫取りの現場には立ち会えなかった。虫取り人の証言は害虫であればどのような虫でもよいとのことであった。
舟・・虫を載せる舟は2艘である。ひとつは前泊港で流し、後の一つは仲筋の浜で沈める舟である。舟の材料は、イビの拝所周辺にあるヤローギ(テリハボク)のY字になった枝が使われた。葉が付いた先端を縛り、茎基にはサンゴ石が結わえられた。
虫どもはビッヴリ゜ガッサ(クワズイモ)の葉に包まれ、舟の中央に載せられたのである。これですべての準備は完了である。
さて、イビの拝所での虫送り祈願のあと舟は二手に分かれ、当方は直ちに仲筋の祭場に急いだ。
浜にある洞窟・・仲筋の祭場は、ウプドゥマリ゜トゥブリから降りた地点にある。浜からは一段上った段丘面の洞窟である。ピンダピィーキ(山羊の穴)とよばれ、普段は山羊に草を食ます場所であるのか。神様がいるという。この前でも祈願がありその後、2人の男が舟を持って浜に降りた。
虫を沈める地点・・浜からイノー内にある特定の岩、カミナカと称されている三角形状の転石が400メートルほどの距離にある。そこまでは海中を徒歩で2人の男が舟を担いで行った。この日のイノーはほぼ膝ぐらいであったが、カミナカ岩が近づくにつれて胸を越すほどの深さであった。ここに虫を沈めて行事は無事終了した。
宮古島狩俣でも旧暦2月には、むシっそーイ(虫払い)がおこなわれた。前の浜の沖合いにある「前離り岩」まで泳いで、害虫が乗せられている舟を流したという。多良間島のウプリによく似た虫送りの行事が報告されている。
多良間島のウプリは、洞窟での祈願があることと、流すのではなく特定の海中まで行って沈めることに特徴があるといえよう。興味が尽きない虫送りの行事である。
2.ウプリに集う人々
多良間島の村をあげて催される年中行事では、ウプリは年の初めの規模の大きな行事であるという。
前泊港近くのイビの拝所がこの祭祀の中心祭場となる。8時30分ごろから祭場の掃除が開始され、準備が整うころ長老がたや字長がみえられ、ウプリ見学の許可をいただいた。
9時を過ぎると、虫取りに出掛けていた人が戻り舟作りが本格化した。虫はクワズイモの葉に包まれている。2艘の舟を作るが、材料はイビの広場周辺に植わっているY字形をしたテリハボクである。葉が付いたままの先端を結わえて舟形とした。その真中に虫の包みを固定して、さらにテリハボクの茎の部分には、やや大きめのサンゴ石が重石として結わえて完成した。
そのころには、イビの祠の前にはゴザが敷かれ、聖域を囲む石囲いの中と外には当日の参加者が着座した。総勢40名ぐらいの方々で男性のみである。そして、ニシャイガッサ(二才頭)により、害虫をこの島から追い出して、今年の農作物が害虫の被害を受けず、りっぱに収穫できることを祈願された。
イビでの祈願が終わると、直ちに仲筋側の虫送りの祭場に移動した。ウプドゥマリトゥブリから降りた段丘にピンダピィーキという洞窟があり、ここでも虫送りの祈願をおこなうのである。ここでは7~8名の参加である。
そして、いよいよ虫を沈めるときがやってきた。聞いたところ、浜からイノーの特定の岩まで歩いていくという。300~400メートルほどの沖合いである。虫送り実行委員の若者2人が舟を担いで歩き出した。当日の天気は気持ちよく晴れはしたが、海に入るには少し寒いようである。イノー内はしばらくは膝ぐらいの深さであったが、目的の岩が近づくにつれ深くなり、沈めた場所は肩まで浸かっていた。満潮時では船を出すという。
大役を終えた2人は、10分ほどで浜から上がり虫を沈めた岩が見える護岸上で直会がはじまった。
長老、字長、ニシャイガッサの人と実行委員のメンバーである。私の前にも伝統料理である重箱料理(厚揚げ、三枚肉、結びこんぶ、かまぼこ、てんぷら)の品が、モンパの葉を皿にして取り分けられた。そして長老方により、今年も無事虫送りが済んで豊作でありましょう、との挨拶がおこなわれた。そして和やかな直会にも参加することができたのである。うりずんの風が心地よく吹く浜辺での直会であった。
このあとさらに、イビの拝所前では直会は延々と続いたのである。ここには、村の幹部や教育委員会関係者、製糖工場長なども臨席していた。
虫送りは筆者が勤めていた天理市内でも、山間の農村地帯で僅かにおこなわれているに過ぎない。近代農業では農薬の普及などで祭りの意義は失われたのである。しかし、同時にそれはムラ共同体の一体感も同時に消失した。 (人文書院より)
【アブシバレー】名護市嘉陽・安部地区
旧暦の4月、名護市嘉陽・安部地区では、アブシバレーという行事が行われます。
琉球王国の時代から続く古い行事です。
バショウの葉や茎で舟をつくり、
「あんまり田畑の作物を食べないでねー!」「作物がすくすく育って豊作になれ!」と願いをこめて、
農作物を食べてしまう生き物(カタツムリや虫など)を乗せて海に流します。
その間、おしゃべりは禁止です。
安部や嘉陽では、昔から伝わる古い行事が受け継がれています。
しかし、今年は中止になる行事もありそうです。
一日でも早く、こうした伝統行事が安心して実施できる日が
来ますように!!



【フムヌン / 虫送り神事】与那国
久部良公民館(崎原敏功館長)は5月16日、フムヌン(穂物忌祭)の祈願を行った。稲穂の出る時期に害虫の被害に遭わないよう願い、虫を海に流す神事で旧暦の4月21日に稲の成長を祈る「ツァバムヌン」と同時に行われる。
クブラバリの高台でニンガイ(祈願)をした後、稲穂を食べてしまうジャンボタニシをクワズイモの葉に包み、かまぼこやナントゥと一緒に全長50センチほどの舟に乗せて海に流した。舟は久部良小学校の児童らが事前に授業で手作りしたもので、皮をむいたバショウの木3本をダイミョウダケを細く削った串で固定し、土台を作った。
参加者は道に寝そべって寝たふりをし、役員の1人が鶏のまねで「コケコッコー」と鳴き、全員が起き上がる「スディ」と呼ばれる儀式を行った。
害虫を乗せた舟は役員が海に流すが、この日は風が強く、場所をダンヌ浜に変更してアンドゥヌチマ(理想郷)へ送り出した。参加した児童らは風にあおられながらも波を越え、進んで行く舟へ「今年もお米が豊かに実りますように」と願いを込めた。 (沖縄タイムズ)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
奄美から八重山までの琉球弧の島々では、田んぼや畑から虫を捕り、芭蕉の葉などで作った小さな舟に虫を乗せ、海に流すという行事があります。この行事のことを民俗学では「虫送り」といい、田畑の害虫であるネズミやバッタ、カタツムリなどを捕らえて海に流して、害虫駆除する行事(『沖縄大百科事典』)であると解説されています。今月は琉球弧の島々で様々な形をとりながら行われている「虫送り」の行事について考えてみます。
「虫送り」の行事は、祭祀の形態が地域によって異なり、統一したイメージで表すのはむつかしいのですが、共通項として、①田畑を害すると思われるものを海へ流す、②家には原則として誰も残ってはいけない、ことなどがあげられます。そのほかに、③火を焚いてはいけないというタブー、④浜辺では競馬や相撲・舟漕ぎ競争などが行なわれる、⑤一年間に生まれた赤ん坊のお祝いをする、⑥豚を除く牛・馬・山羊などの家畜も浜へ下ろす、ことなどが多くの地域で行われています。
①の「海へ流すもの」には、ネズミやバッタ、カタツムリなどがありますが、西表島ではイノシシの足跡も土ごと削りとって海に流します。ネズミやイノシシは虫ではありませんが、「虫送り」の概念の範疇に入ります。この海へ流す「もの」たちは、単なる災厄を与える「もの」なのでしょうか。久米島に伝わる『久米仲里旧記』に記載されている「浜降りのときのまじない言」には、ネズミは「太陽の子」だと歌われています。魂(マブイ)を落としたとき、つまり魂が遊離したときにする、マブヤーグミ(魂篭め)の儀式では、バッタなどの虫は、落としたマブイのシンボルとして、家に持ち帰るものになっています。イノシシは、『古事記』のヤマトタケルの東伐の項に、伊吹の山の神として出現します。流される「もの」たちは、いずれも霊的な存在であることがわかります。
②の「家には原則として誰も残ってはいけない」、ということは、居住空間としてのシマ(村落共同体)が一時的に無人に近い状態になることを意味しています。なぜシマを無人の状態にするのかというと、神を迎える場に人間はいてはならなかったからです。神を迎えることができるのは、「神の花嫁」だけだったのです。それは聖なる婚姻でした。神は婚姻のために地上を訪問するのです。そのことのみが人間と神を結ぶ接点でした。その聖なる婚姻の場に人間は立ち会ってはならなかったのです。
国頭郡では、「虫送り」の日は裕福な家だけが留守番を置きます。「虫送り」に参加できない病人なども家の中にいてはいけない。門の前か庭にいなければならない。もし家の中にだれか残っていたのならば、その人はハブに咬まれてしまう(島袋源七『山原の土俗』)といわれています。ハブに咬まれてしまうということは、その日家を訪問するのはハブだということでしょう。③の火を焚いてはいけないというタブーは、水の神である蛇に関するタブーであるような気がします。このような危険な日に、留守番を置くということはどういうことなのでしょうか。羽地村(現在は名護市)の裕福な家に二人の美人の姉妹がいて、この日に留守番を命じられて家に残っていたという伝承があります(島袋源七『山原の土俗』)。なぜこの日に姉妹が留守番を命じられたのでしょうか。それはある種の役割を期待されていたからだと思われます。神を迎え入れることによって、家を富み栄えさせるという役割が。つまり、この姉妹は「神の花嫁」の役割を期待されていたのだと考えられます。奄美と八重山では「虫送り」の日は各家に一人の留守番を残すといいますから、より古い形では、裕福な家だけではなく、すべての家に「神の花嫁」を残したという可能性を想定することができます。
④の競馬や相撲・舟漕ぎ競争などは、娘たちが神を迎え入れている間に、青年たちが力の限りに一年の豊穣を招き寄せるための祭祀であったものと思われます。
八重山の「虫送り」の祭りの日には、浜辺で寝るという儀式がありました。地域によって多少の違いはあるのですが、短いところでは20分、長いところでは3時間ほど浜辺で寝る真似をするのです。寝るというのは、魂が身体を離れている状態です。それがなにを意味しているのかというと、魂の切り替えを行ったんだろうと思います。寝ている間に古い魂を流し捨て、新しい魂を身に着けるための儀式だったのではないだろうかという気がします。あるいは仮死状態を演じていたのかもしれません。新しく生まれ変わるために。
⑤の新生児のお祝いは、新生児に初めての魂の切り替えを行い、人間社会への第一歩を踏み出させるという儀式だったと思われます。
⑥の豚を除く牛・馬・山羊などの家畜も浜に下ろすことは、家畜の魂を切り替えるためなのか、それとも水の神と相性が悪いために遠慮したのか、今のところわかりません。豚は琉球弧では霊的に特別な意味を帯びています。夜中に帰ってきたときは、豚小屋で豚を鳴かせると魔物を追い払うとか、マブイを落としたとき、まだマブイが近所をうろついている間は豚小屋を拝むとマブイが戻ってくるといわれています。豚小屋に棲むフール神は家の中でもっとも霊力の高い神とされています。魂に関する儀式が家の中で行なわれていたのならば、豚の霊力も必要だったのかもしれません。
「虫送り」は神を送るための行事だったのだろうと思われます。だとしたら、神を迎えるための行事があったはずですが、それは省略されているようです。神は魂たちを引き連れてやってきましたが、その魂は虫に乗っていました。人間たちは虫から魂を受け取ると、古い魂を虫たちに乗せて水平線の彼方へ帰しました。
農耕が始まったとき、魂は栽培植物の種子に込められるようになり、虫たちから魂を受け取る儀式が省略されてしまいました。逆に虫たちは、農耕を害するものとして、追放される身の上になったのです。人間たちの心の中で。
『おきなわJOHO』1998年4月号
今回知り得た現存すると思われる全国の虫送り行事73件の仕分けを
・松明を主体とした虫送り
・虫かご、虫舟などを主体とした虫送り
・人形(主にサネモリ)を主体とした虫送り
・ほか
という大変大雑把な形態で仕分けし、その割合を算出し多い順に並べてみると
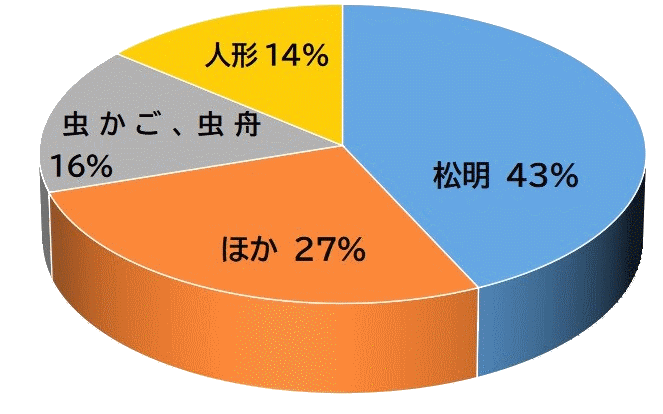
①松明を主体とした虫送り=43 %
➁ほか=27%
③虫かご、虫舟などを主体とした虫送り=16%
④人形(サネモリや人型)を主体とした虫送り=14%
という結果が出ました。
また、それらを地域別の形態による割合を多い順に並べてみると
てみると
【北日本 】(13件の割合)

①虫かご、虫舟などを主体とした虫送 / ほか (同率各46%)
➁人形(人型)を主体とした虫送り(8%)
③松明を主体とした虫送り(0%)
【東日本】 (29件の割合)
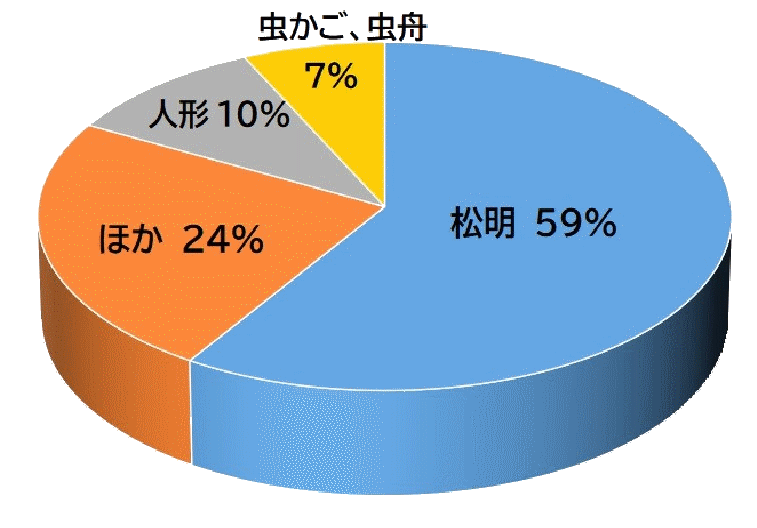
①松明を主体とした虫送り (59%)
➁ほか (24%)
③人形(サネモリ))を主体とした虫送り(10%)
④虫かご、虫舟などを主体とした虫送(7%)
【西日本】 (31件の割合)
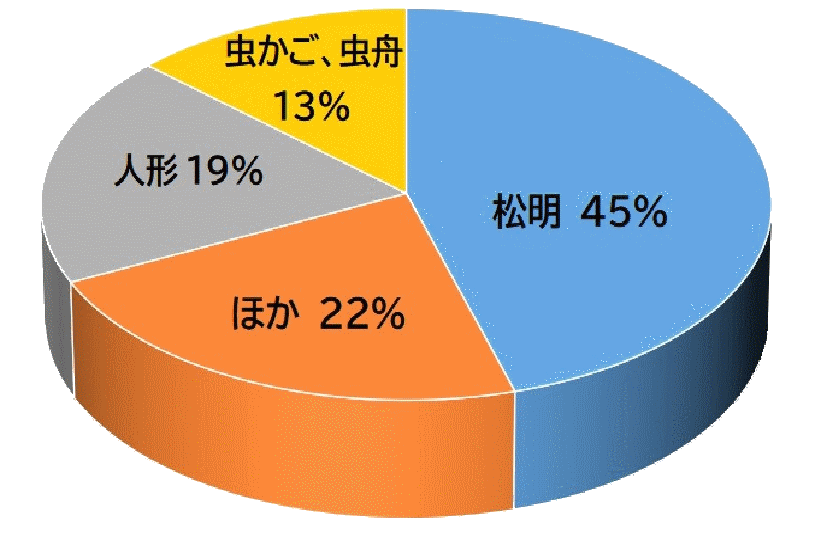
①松明を主体とした虫送り (45%)
➁ほか (22%)
③人形(サネモリ))を主体とした虫送り(19%)
④虫かご、虫舟などを主体とした虫送(13%)
という結果になりました。
大雑把に分けると、東日本、西日本では松明が多く使われ、田畑を巡行し実質的に虫を焼き殺すという行為を伴っているのに対し、北日本(西日本でも奄美~沖縄)では虫を生きたまま虫かごや舟形に入れ流すという形態の違いと、その背景にある「何か」の差にとても興味がそそられます。
また今回、全国の虫送りについて調べる以前、会津管内に残存する虫送り行事では形態は違えど「虫かご」を作っている地区は多く、また「虫送りなのだから、当地区と同じような虫かごを作っているところも”ソコソコ在るのではないか”」という思い込みがありましたが、蓋を開けてみると少数派、且つ限定的であることが明らかになり驚いています。
そして同じ系統であってもであってもそれぞれの地域差があり、また同じ地域でも系統、形態が異なるものが共存していることにも驚いています。
更には前出の「ほか」の項目内の形態には、ほぼ同じものが存在せず、多種多様で幅広く、ある意味捉えどころのない多様性が見られるのもこの行事の特筆すべき点であると思っています。
われらが「高橋の虫送り」もしかり。
私の住む冑地区で作られてきた、縄文を感じさせるプリミティブな虫かご。そして隣村、尾岐窪で作られてきた弥生の匂いを感じさせるスマートで繊細な虫かご・・・同じ地域なのに、なぜこうも違いが生じ、その違いを良しとして共存して来たのか・・・。
この「沼」は簡単に抜けられそうにありません。
(筆者 noribo)
