




資料室
material room
自然界の生き物や環境と暮らしに関わる色々な情報をご案内
里山環境荒廃の原因
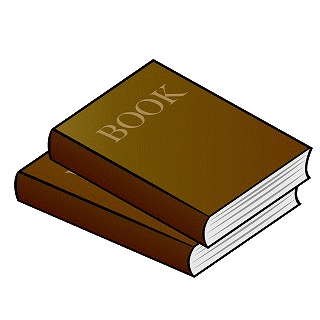
里山荒廃の歴史と時代背景
日本生態学会による「里山のこれまでとこれから」という冊子内に、生態系管理工学教授 鎌田 磨人さんによる、とても分かりやすい文章が掲載されていますので、以下引用してご紹介します。
◇「里山の今とこれから」より
里山の危機
1945年に太平洋戦争の終戦を迎えた後日本は荒廃した国土を、めざましい勢いで復興し、 そして、1955年から高度経済成長期に突入しました。
鉄鋼・造船・自動車・電気機械・化学・石油化学・合成繊維維などの産業部門が急速に発展し、1975年までの間 年平均経済成長率は10%を超えていました。
そのような産業の発展を支えたのは 農村から都市圏へと移り住んだ人々でした。
1960~1975年の15年間に、東京、大阪、名古屋の三大都市圏に1533万人が流入しました。そして、都市圏に移り住む人たちのために、都市周辺の里山が造成されて団地(ニュータウン)が造られました。
こうした復興・経済発展によってて増加する木材需要に応えていくた拡大造林(※)も推し進められました。
広葉樹の森林は スギやヒノキの人工連へと転換されていきました。
その一方で中山間地域の農村では人口が激減し、過疎化が進行しましました。
1950年に300万戸あった専業農家は1970年には85万戸に激減しました。減少した労働力を補い、また、農作業の重労働から解放したのはトラクターやコンバインであり、化学肥料でした。
また、日本中のほとんどの家庭の燃料は、ガスや石油、あるいは電気にとってかわりました。
この間、貿易の自由化によつて、木材も海外から日本に流れこむようになりました。
経済発展に伴う人件費の高騰、人口流出による中山間地域での働き手が少なくなったこともあいまって、安価な外材の輸入量が飛躍的に増加したのです。
高度経済成長期に産み出されたグローバル化、少子高齢化、都市域の拡大と農村の過疎化といった社会の変化、その傾向は今でも続いています。そして里山景観を大きく変貌させています。
里山の消失
都市域周辺での開発は、里山そのものを焼失させてゆきます、また里山から得てきた木材、茅、薪炭などは利用されなくなりました。建築材は輸入材が使われるようになり、1055年には95%であった木材の自給率は、2000年には18%まで落ち込みました。
その後自給率が上昇してきていますが、それでも2013年の自給率は28%にとどまっています。このように、今、ほとんどの里山が放置されたままになっています。
多くの草地は遷移によって藪や森林になってしまいました。今、日本にはごくわずかの草地しか残っていません。アカマツ林やカシ・ナラ林も林内に樹木が繁茂するようになり、暗い森林へと変化しています。
(以上引用)
(※拡大造林=昭和戦後期の国策で、復興のため不足した木材を補うため、明治期に造成された広葉樹中心の林を、木材により適したスギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツなどの針葉樹中心の林へと変化させてきた林業政策 / 以上注釈事務局)
