連載 虫送り・虫供養考 Ⅱ
- noribo
- 2025年7月11日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年8月3日
虫送りの歴史と起源 part-2
現在行なわれている「虫送り」と同じであるか否かは別として、今から2,700年以上前から既に、稲作に関わる虫よけの神事が行なわれていた事はどうやら間違いないようだ。
では、この虫送り神事の誕生に深く関わる稲作はいつ頃から始まったのか。
稲作の起源は、中国の江西省や湖南省の遺跡で1万年以上前の稲籾が多数発見されている事から、この頃には焼畑による陸稲栽培が行われていたと考えられている。
尚、今の「日本のお米」であるジャポニカ米の栽培は、中国大陸の長江の中・下流域で始まったとされている。
(追記 / 『DNAが語る稲作文明』の著者、静岡大学農学部助教授の佐藤洋一郎氏は中国の長江下流の河姆渡(かぼと)という地栽培稲だけでなく、栽培稲の先祖に当る野生稲の痕跡が発見され、さらに野生稲から栽培稲へと変っていった痕跡も発見されています。
以前は7000年前という年代の真偽が問われたこともありましたが、現在、最も信頼できる手法を用いて出土したモミを測定したところ、確かにその時代のものだと証明されています。それで私は、稲作の起源は長江流域にあるのではと思うようになりました。」と自身のDNA研究による考察を行っている。
その後「長江に沿って東へ進み、やがて朝鮮半島を経て西日本に上陸」「長江下流から北九州の対馬を越えて直接海より渡来」「台湾を経由し島伝い」「朝鮮半島から直接日本海沿岸にたどり着いた」などさまざまな説があるが、いずれかの説、一つではなく複数のルートで伝来した可能性も高い。

いずれにせよ大陸から稲作が伝わった時代を、現在では「縄文後期~晩期」としている。今から3,000年ほど前の事である。
そして2,700年ほど前、神武天皇が即位し、神代は幕を閉じ、現在の日本の歴史が始まる。
その後、渡来の民が徐々に増加し、紀元後3世紀(2,300年前)には卑弥呼を女王とする倭国、すなわち邪馬台国が誕生する。
そしてこの頃には、稲作栽培(水田農耕による)の農業社会もほぼ完成されていたと考えられている。
米は他のどの栽培植物よりも高収量であり、増加する人民には、その生命を支えるために格好の食材であったのと同時に、国造りを進めるため人民をコントロールする必要のあった権力者にとって必要不可欠な食材だった。
しかし効率の良い水田農耕による稲作により米を増産するためには、縄文末期に行なわれていたとされる焼き畑による移動式の陸稲栽培とは環境を大きく作りかえる必要があった。
同じ場所で稲を育てる田を作るための土木工事を行い、畦を作り、水を張らなければならない。そのための水路も必要だ。
しかしその農法は人間にとって都合の悪いいきものを増やす結果となった。
前出の焼き畑農法に代表される移動式の農業では、農作物を餌とする虫が増殖する前に耕作を中断して別の場所に移ったり、農地に火を入れたりするため、害虫の発生に悩まされることはあまりなかったと考えられる。
では同じ農作物を毎年同じ場所で栽培する定住型農耕はどうだろう ?
衆知のとおり、弥生時代以降になるとその定住型農耕が広まっていくわけだが、その食材が同じ場所で作られ、食べられれば、それは我々人間の生命維持の担保となり、暮らしの安心、安定につながり、子孫繁栄の営みが活性化する。
それは自然界に生きるものも同じである。生きるため、そして子孫を残すためには先ず食い物が必要であり、それが確保できる場があれば、そこは格好の「餌場」となり繁殖が活性化し生命体が増加する。そのいきものの中には人間にとって都合の悪いものも存在するのは当然の事である。
※この見解は人間の自己中心的捉え方である。 地球に生きるものは細菌類を省き、すべて何かしらの栄養となるものををエネルギーに変えて生きている。それが自然の摂理であり人間という生命体もその一部にしか他ならない。と理解すべきである。
では、当時の人々はその事をどう捉えていたのであろうか ?
次回はその辺りへと考察を進めたい。
※参考文献
・害虫の誕生―虫からみた日本史、 瀬戸口明久 著
・亀田製菓 HP お米の国の物語
・クボタグループ HP 稲作の歴史
・米が育んだ日本の歴史と文化 / 佐藤洋一郎・京都府立大学文学部特別専任教授
ほか



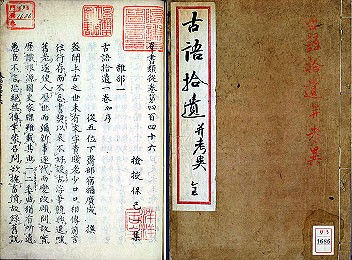
コメント